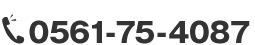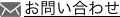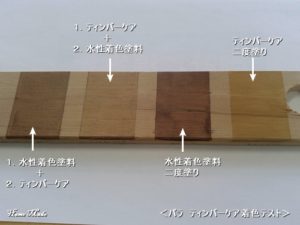輸入サッシの技術を導入して製造された樹脂製シングルハング窓。
窓の側枠の溝に仕込まれたコイル・バランサーが破断した為、静岡県沼津市まで交換作業にやってきました。
IMS(アイエムエス)カナダという九州にあったサッシメーカーの窓なんですが、既に倒産した為アフター・メンテナンスはありません。
そこで私たち ホームメイドが、アメリカから交換部品を取り寄せて遠く名古屋から車を飛ばして伺いました。
今回は、交換作業に使う新たな工具を持ち込みました。その名も、ウィンドウ・フレーム・エキスパンダー。この工具を窓枠の溝の中に入れてハンドルを回していくと、溝が広がってバランサーを取り出すことが出来るという専用工具です。
初めて作業に使用しましたので、少しずつハンドルを回して慎重に作業を進めました。見事コイル・バランサーは溝から外れ、新しいものに交換することが出来ました。
やっぱり、アメリカには便利な道具があるものですね。勿論、他にもやり方はあるのですが、樹脂の窓枠を傷めてしまうリスクがありますから、慣れや感が必要です。
これからは、この専用工具を利用して輸入の上げ下げ窓の修理をどんどんやっていきますよぉ~。それにしても、こんな道具を持っている輸入住宅ビルダーは、どれだけいるんでしょうかねぇ。
<関連記事>: 遠く沼津市へ調査に伺いました (2016年11月16日)
輸入住宅の新築やメンテナンス、コンサルやコーディネートをして欲しい、私と話をしたいという方は、お問い合わせ下さい。全国どこでもご相談を受け付けます。
窓やドアの修理・メンテナンスの概要は、リペア&メンテナンスのページをご覧下さい。尚、相談や問い合わせの前には、日々更新する記事をいくつかご覧の上適否をご判断願います。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。古い日付の記事は、内容が更新されている場合がありますので、出来るだけ新しい記事を参照下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。